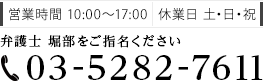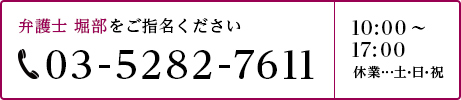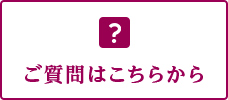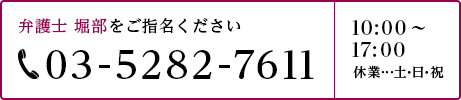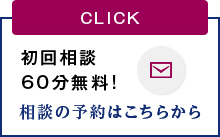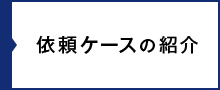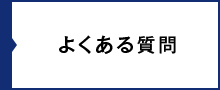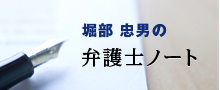手形法
2015.10.07更新
こんにちは。弁護士の堀部忠男です。
民法や刑法等戦前から引き続き使用されている法律の多くは、戦後も長い間文語体カタカナ書きのものを使っていましたが、刑法は20年近く前に、民法は10年くらい前に、法律の内容はほぼ同一のまま表記だけが口語体のひらがな書きに変更されました。現在では文語体カタカナ書きの法律は少なくなってきましたが、よく利用される法律の中では手形法がまだ文語体のカタカナ書きのままです。手形法は法学部/法科大学院では商法の一科目として必修とされている場合が多いと思いますし、現在では電子記録債権(でんさい)が登場して年々流通量は減少しつつあるようですが、手形は今でも広く利用されています。そのような比較的主要な法律であるにもかかわらず、文語体カタカナ書きのままであるのは、手形法は手形の国際統一のためのジュネーブ手形法統一条約に基づき制定されたものであるので、内容を変更することはほとんどなく改正を考える機会がなかったからではないかと思います。ちなみに、条約の加盟国の手形法はほぼ同じになっているはずです。
手形は簡易な手形訴訟も利用できますので、通常の債権よりは回収しやすい面はあります。しかし、一般に裏書人がいる場合は少ないので、回収できるかどうかは結局は振出人の資力次第になります。そのため、不渡りになった場合は直ちに弁護士と相談して回収のための行動を始める必要があります。
投稿者: