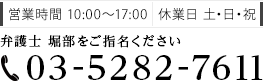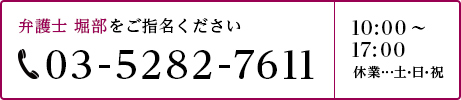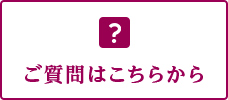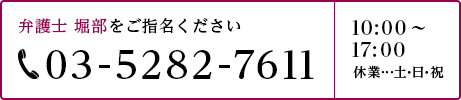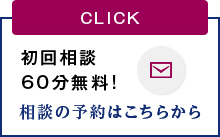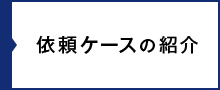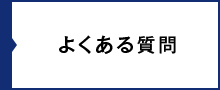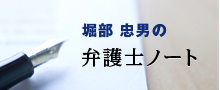みなさん、こんにちは。弁護士の堀部忠男(ほりべ ただお)です。
前回の記載の中に、特例有限会社という言葉が出てきましたので、今回は特例有限会社について書こうと思います。
前回、特例有限会社が出てきた箇所は、株式会社と書いてある後に括弧書きで特例有限会社を除外する記述になっていました。世間には有限会社はたくさん存在していますが、株式会社と有限会社は別ものではないかと思った方もいらっしゃるかもしれません。確かに、2006年5月に「会社法」という名前の法律が施行される前までは、株式会社と有限会社は別の種類の会社組織でした。株式会社については「商法」に規定され、有限会社については「有限会社法」という法律がありました。
それが、会社法の施行に伴って、有限会社の制度は廃止され、それまでに設立されていた有限会社は株式会社として存続することになりました。有限会社は株式会社という名称を使用して普通の株式会社になることもできますが、株式会社という扱いになっても有限会社という名称を使用し続けることも選択でき、そのような会社は従前の有限会社のときと同じような制度を利用できることを別の法律で規定し、そのような会社を特例有限会社と呼ぶことになりました。そのため、新たに有限会社を設立することはできませんが、従前から存在した有限会社という名称の会社が今でもたくさん残っています。
特例有限会社は休眠会社の規定が適用除外とされていますので、休眠会社だとして解散とみなされることはないという仕組みになっています。