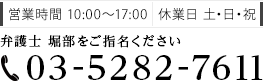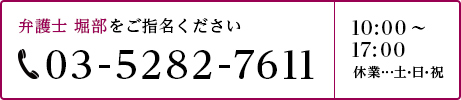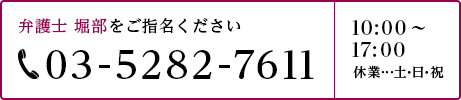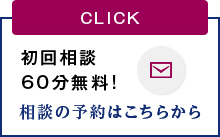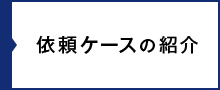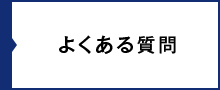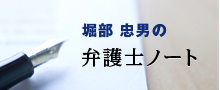債権法
2015.09.30更新
話の内容は、前回の続きです。
民法の条文は、多くの場面に共通して使う一般的・抽象的な規定をまとめて前に置き、後ろに個別の具体的な規定を置く、パンデクテン方式と呼ばれる形式で配置されています。民法典の最初にある第一編は総則で、第二編が物権、第三編が債権で、第四編は親族、第五編が相続となっています。第三編の債権の中にも、第一章に総則があり、第二章が契約で、他に第五章まであります。第二章の契約の中には、さらに第一節に総則があり、第二節以降に売買、賃貸借などの契約の規定が第十四節まであります。第二節から第十四節までに規定されている各契約は、典型契約と呼ばれます。有名契約と呼ばれることもあります。主要な契約である売買と賃貸借の節では更に、それぞれ第一款に総則を置いています。法学部や法科大学院での授業は、主として民法の総則に関する講義を民法総論、第三編債権の中の総則に関する講義を債権総論、債権の中の第二章から第五章に関する講義を債権各論として開講されている場合が多いと思います。
今回の民法改正(債権法改正)では、第三編の条文の改正が主ですが、第一編の総則の条文の中にも改正されるものがあります。パンデクテン方式は、条文作成の場面では効率が良いですし、体系的にもすっきりしている点はよいのですが、実際の事案に条文を当てはめようとしたときに、使用する条文があちらこちらに散らばる場合が多くなってしまい慣れないとかなり分かりにくいというのが難点です。
投稿者: