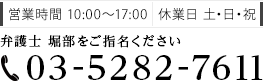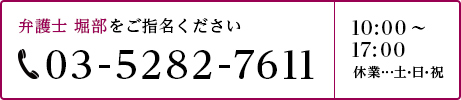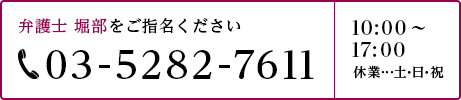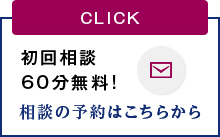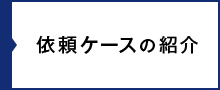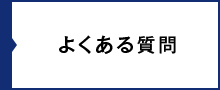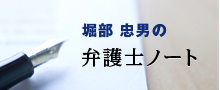こんにちは。弁護士の堀部忠男です。
内容は、前回、前々回の続きです。
民法を改正しようとする目的は2つあり、①”社会・経済の変化への対応を図ること”と、②”国民一般に分かり易いものにすること”です。
主な改正点をこれらの目的に分類しながら述べてみます。
”社会・経済の変化への対応を図る”目的からの主な改正点は、①保証、②債権の譲渡、③消滅時効、④法定利率などです。
”国民一般に分かり易いものにする”目的からの主な改正点は、①動機の錯誤(勘違い)、②履行不能(物が壊れて引き渡せなくなった場合など)、③損害賠償義務の免責要件、④賃貸者の敷金・原状回復義務などです。
それ以外の理論的な整理に基づく改正点としては、①契約の解除、②危険負担(履行不能のうち、災害等により物が壊れた場合)、③詐害行為取消権と債権者代位権(債権の回収に役立つ債権者の権利)、④瑕疵担保責任(欠陥がある場合)などです。
どのあたりの条文を改正するかという観点から言えば、上記の改正点の多くは第三編債権の中の総則の部分ですが、契約の部分の改正もありますし、消滅時効や動機の錯誤は第一編の総則の改正です。